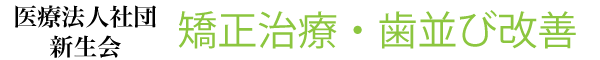良くない歯並び
 過蓋口咬(オーバーバイト)
過蓋口咬(オーバーバイト)
 出っ歯(上顎前突)
出っ歯(上顎前突)
 乱ぐい歯(叢生)歯が重なって生えている
乱ぐい歯(叢生)歯が重なって生えている
 開咬(口を閉じたときに隙間がある)
開咬(口を閉じたときに隙間がある)
不正咬合のトラブル
歯並びや咬み合わせが悪いことを「不正咬合(ふせいこうごう)」といいます。様々な原因がありますが、子供の頃の習慣や癖が影響していることも多々あります。
- よくかまない
- 子供のころに柔らかい食べ物を好んで食べていると噛む回数が少ないため、顎がきちんと発達しない場合があります。顎が発達しないと、歯が生えるスペースがないため、ずれたり、重なって生えることもあります。
- 習慣や癖
- 3~4歳を過ぎても指しゃぶりをしていませんか?成長過程で徐々に指しゃぶりをやめないと、常に前歯が出る状況になり、歯並びが悪くなります。その他にも、唇を噛んだり、爪を噛んだり、頬をつくなどの癖は歯並びに影響します。
- 遺伝
- 一般的に容姿が両親に似ることがありますが、特に出っ歯や受け口などの顔貌が遺伝子する可能性が高いといわれています。
- 病気
- 扁桃腺の腫れや、慢性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などで鼻呼吸ができないお子様は、口呼吸となり、不正咬合の原因になります。
- 歯の治療
- 虫歯治療で、合わない補綴物や義歯をつけていたり、抜歯後その箇所を放置したり、親知らずが歯並びを押している場合なども歯並びが悪くなる場合があります。
不正咬合が全身へ影響を及ぼすことも
- 顎
- 顎関節症(顎の関節が痛い、口が大きく開けられない)の原因に不正咬合があります。顎がきちんと成長せず、上下のバランスが悪くなることもあります。
- 歯と歯肉
- 不正咬合は、歯ブラシが届きづらく、磨き残しが発生しやすくなります。プラークや歯石により歯周ポケットができ、歯周病にもなりやすくなります。
- 発音障害
- 受け口や開咬の方は、サ行、タ行、ラ行の発音がうまくできません。
- 消化不良
- 咬み合わせが悪いと、しっかり噛んで飲み込んでいないため、胃腸に負担がかかります。
- なんとなくだるい
- 肩こりがひどい、頭痛が頻発する、イライラする時が多い、すぐ疲れるなど、不調の原因は不正咬合かもしれません。
- 顔貌
- 不正咬合は顔貌にも影響します。受け口などは、顎が前に出ている状態です。顎を下げ、上下が正しい位置になるとフェイスラインも綺麗になります
歯並びを良くするということ
矯正の目的は、歯並びをきれいにすることだけではありません。きれいな歯並びと、何よりお口の中の機能を改善することです。よく噛めるようにし、モノを飲み込み、発音を正しくする。これが矯正の本当の目的です。